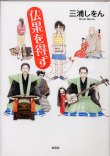2008/02/15
三浦しをんの新作だから、というのも確かにポイントではありますが、正直言うとこの作品を手に取ったのは表紙が勝田さんの絵だったからです。
本屋で平積みになってるのを見た瞬間、「あ!!」と思う間もなく目は釘付け手は伸びる。よく見ると右上に「三浦しをん」の文字。なるほど今度は文楽か……それで装画に勝田さんのチョイスとは、涙が出るくらいによく分かってらっしゃる。
この布陣で攻められて、手を出さずにいられるはずがないでしょう。
主人公は研修所出身の若手大夫、笹本健大夫。
健がある日師匠である銀大夫(人間国宝)から「おまはん、六月から兎一郎と組みぃ」と、変わり者と評判の三味線と組まされるところから物語は始まります。
そして紆余曲折を経て健大夫は大夫として、またひとりの男として、そして人間として成長していく──という、真っ当な青春小説です。
その各エピソードが、その時々の公演演目と絡まって展開されていきます。
実生活での困りごとと、演目がリンクするのですね。
この演目とは……このキャラクタとは……と悩み、得た答えが、そのまま現実にもフィードバックされる、という。そのまた逆もしかり。
それが、各章ごとにぴたっとおさまっていく。
小説としてのエピソードと、文楽の演目の内容があまりにもきれいにはまりすぎているため、少しできすぎ感が漂うのが、もったいなかった点でした。
真っ当な青春小説と書きましたが、この作品は、それと同時に青春小説に擬態した初心者のための文楽解説本といっても差し支えないと思います。
しかし、そこはさすがの三浦しをん。
人間関係が実に秀逸。
有り体に言えば萌えた。萌えに萌えた。
情熱はあるが実力も人間性もまだまだ未熟な大夫。
芸のことしか頭にない変わり者だが実力は一流の三味線。
このふたりの芸に賭ける情熱たるや、その他のなにものをも圧倒します。
そこにある信じられないくらいに強いつながりは、しかし、芸の上でのみ成り立つものです。友情とか親愛とか、そんな単純なものでは決してない。
これこそやおい! 健大夫の語りと兎一郎の三味線が互いに互いを認め高めあっていく場面は、もう、鳥肌ものです。ハァハァしてしまいます。
そして、その関係性は二人だけに留まりません。
なんといったって、そこは芸の世界。芸に一生を捧げた(もしくは、捧げる覚悟を持つ)ものだけが生き残る世界です。周りを見渡せばそういう人しかいないわけです。
ちょっとねぇ、これはものすごいぞくぞくしますよ。
キャラクタひとりひとりが魅力的、というのではないのです。
単体で見ると、別になんてことのない人たちばかり。
でも、そういう人たちが、「芸」を通じて見せる関係性の多様性と熱さ。
それが大きな魅力となっていました。
そして、この作品のもうひとつの魅力は、劇の力を全肯定していることです。
健大夫は、ただ単純に、それこそ盲目的に劇の持つ力を信じています。劇の持つ多様性を。劇の持つ可能性を。
クライマックス、『仮名手本忠臣蔵』六段目「早野勘平腹切りの段」を語りながら、健大夫はその劇の力を確信します。
----------------------------------------------
俺が語る声も、兎一兄さんの三味線も、人形を遣う十吾の息づかいも、客席からの熱気も、すべてが勘平という架空の人物のための糧に過ぎない。
舞台は爆発寸前の高揚を秘め、健はその場に居合わせた人々が、大きな渦に巻きこまれていくのを感じた。抗いようがない。舞台を主導していたはずの自分の声すら、もはや制御不能な巨大な渦の一角となった。
これが劇だ。時空を超え、立場の異なる人々の心をひとつの場所へと導く、これが劇の力だ。
(中略)
健は内心で叫ぶ。
仏に義太夫が語れるか。単なる器に過ぎぬ人形に、死人が魂を吹き込めるか。
(中略)
万雷の拍手。ミラちゃんが、真智が、生まれた場所も時間も生きてきた境遇もちがう人々が、舞台に向けて一心に手を叩いている。忠義を描くのではなく、忠義に翻弄されるひとの心の苦しみと葛藤を描いた『仮名手本忠臣蔵』は、二百五十年以上のときを経ていまも生きる。
----------------------------------------------
ここで泣いた。もう、号泣した。
人間の、創作に情熱を賭けるすべての理由がここにはあった。
そして、それを鑑賞するすべての理由も。
あまりにもうれしくて、うれしくて、うれしくて、泣きながら笑えてきて大変だった。
文楽を愛する人はもちろん、芝居や舞台を愛する人も、音楽でも小説でもマンガでも映画でもなんでもいいから、とにかく創作を愛するすべての人に読んでほしいと思った。
キャラクタやストーリー展開の単調さや、全体的に小振りできれいにまとまりすぎている物足りなさ、それら欠点を補ってあまりある魅力が、この作品にはありますよ。
本屋で平積みになってるのを見た瞬間、「あ!!」と思う間もなく目は釘付け手は伸びる。よく見ると右上に「三浦しをん」の文字。なるほど今度は文楽か……それで装画に勝田さんのチョイスとは、涙が出るくらいによく分かってらっしゃる。
この布陣で攻められて、手を出さずにいられるはずがないでしょう。
主人公は研修所出身の若手大夫、笹本健大夫。
健がある日師匠である銀大夫(人間国宝)から「おまはん、六月から兎一郎と組みぃ」と、変わり者と評判の三味線と組まされるところから物語は始まります。
そして紆余曲折を経て健大夫は大夫として、またひとりの男として、そして人間として成長していく──という、真っ当な青春小説です。
その各エピソードが、その時々の公演演目と絡まって展開されていきます。
実生活での困りごとと、演目がリンクするのですね。
この演目とは……このキャラクタとは……と悩み、得た答えが、そのまま現実にもフィードバックされる、という。そのまた逆もしかり。
それが、各章ごとにぴたっとおさまっていく。
小説としてのエピソードと、文楽の演目の内容があまりにもきれいにはまりすぎているため、少しできすぎ感が漂うのが、もったいなかった点でした。
真っ当な青春小説と書きましたが、この作品は、それと同時に青春小説に擬態した初心者のための文楽解説本といっても差し支えないと思います。
しかし、そこはさすがの三浦しをん。
人間関係が実に秀逸。
有り体に言えば萌えた。萌えに萌えた。
情熱はあるが実力も人間性もまだまだ未熟な大夫。
芸のことしか頭にない変わり者だが実力は一流の三味線。
このふたりの芸に賭ける情熱たるや、その他のなにものをも圧倒します。
そこにある信じられないくらいに強いつながりは、しかし、芸の上でのみ成り立つものです。友情とか親愛とか、そんな単純なものでは決してない。
これこそやおい! 健大夫の語りと兎一郎の三味線が互いに互いを認め高めあっていく場面は、もう、鳥肌ものです。ハァハァしてしまいます。
そして、その関係性は二人だけに留まりません。
なんといったって、そこは芸の世界。芸に一生を捧げた(もしくは、捧げる覚悟を持つ)ものだけが生き残る世界です。周りを見渡せばそういう人しかいないわけです。
ちょっとねぇ、これはものすごいぞくぞくしますよ。
キャラクタひとりひとりが魅力的、というのではないのです。
単体で見ると、別になんてことのない人たちばかり。
でも、そういう人たちが、「芸」を通じて見せる関係性の多様性と熱さ。
それが大きな魅力となっていました。
そして、この作品のもうひとつの魅力は、劇の力を全肯定していることです。
健大夫は、ただ単純に、それこそ盲目的に劇の持つ力を信じています。劇の持つ多様性を。劇の持つ可能性を。
クライマックス、『仮名手本忠臣蔵』六段目「早野勘平腹切りの段」を語りながら、健大夫はその劇の力を確信します。
----------------------------------------------
俺が語る声も、兎一兄さんの三味線も、人形を遣う十吾の息づかいも、客席からの熱気も、すべてが勘平という架空の人物のための糧に過ぎない。
舞台は爆発寸前の高揚を秘め、健はその場に居合わせた人々が、大きな渦に巻きこまれていくのを感じた。抗いようがない。舞台を主導していたはずの自分の声すら、もはや制御不能な巨大な渦の一角となった。
これが劇だ。時空を超え、立場の異なる人々の心をひとつの場所へと導く、これが劇の力だ。
(中略)
健は内心で叫ぶ。
仏に義太夫が語れるか。単なる器に過ぎぬ人形に、死人が魂を吹き込めるか。
(中略)
万雷の拍手。ミラちゃんが、真智が、生まれた場所も時間も生きてきた境遇もちがう人々が、舞台に向けて一心に手を叩いている。忠義を描くのではなく、忠義に翻弄されるひとの心の苦しみと葛藤を描いた『仮名手本忠臣蔵』は、二百五十年以上のときを経ていまも生きる。
----------------------------------------------
ここで泣いた。もう、号泣した。
人間の、創作に情熱を賭けるすべての理由がここにはあった。
そして、それを鑑賞するすべての理由も。
あまりにもうれしくて、うれしくて、うれしくて、泣きながら笑えてきて大変だった。
文楽を愛する人はもちろん、芝居や舞台を愛する人も、音楽でも小説でもマンガでも映画でもなんでもいいから、とにかく創作を愛するすべての人に読んでほしいと思った。
キャラクタやストーリー展開の単調さや、全体的に小振りできれいにまとまりすぎている物足りなさ、それら欠点を補ってあまりある魅力が、この作品にはありますよ。
この記事にコメントする
PR
カレンダー
最新記事
(12/16)
(01/25)
(11/03)
(10/31)
(10/11)
(10/11)
(10/11)
(08/28)
(07/25)
(07/12)
アーカイブ