2007/01/16
上橋菜穂子 / 偕成社
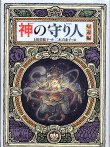
ロタ国のことはロタ人にまかせろという忠告を無視し、アスラを連れ逃げるバルサ。執拗にアスラを追う謎の女シハナはバルサに重傷を負わせる。アスラは「神の守り人」なのか。それとも「災いの子」か。バルサはアスラを助けられるのだろうか。
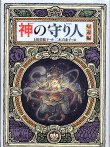
ロタ国のことはロタ人にまかせろという忠告を無視し、アスラを連れ逃げるバルサ。執拗にアスラを追う謎の女シハナはバルサに重傷を負わせる。アスラは「神の守り人」なのか。それとも「災いの子」か。バルサはアスラを助けられるのだろうか。
とうとうアスラが「神」の力を自分の意思で引き起こしてしまいます。
圧倒的な暴力は、快感です。
すべてを服従させ、従わせることはとてつもなく甘美な麻薬です。
幼いアスラがそうした力を手にしたとき、それに呑み込まれてしまうのは仕方のないことだとも言えます。
しかし、バルサは決してそれを許しません。
それは、暴力ではなにも解決しない、とか、人を殺してはいけない、とか、そういう通り一遍の善悪論ではなく(や、もちろんそれも多分に含まれてはいますが)、自らの経験と過去からそれを許さないのです。というより、許したくない、という方が正確。
短槍を人に向けるとということは、自らの心に向けているのと同じ。
人を傷つける、ましてや殺めるということは、軽々しく扱えるようなことではないのです。
それが、重い。
とても重い思い。
バルサはそれを言葉を尽くして語りかけるようなことはしません。
わずかな慈しみの言葉と、悲しげな瞳、自らの生きる姿を、アスラに見せるだけです。
しかし、そうして生きてきたバルサの姿は、なによりの言葉となり、アスラの心に染みこんでいきます。
「神の守り人」は『来訪編』と『帰還編』という風に命名されています。
作者本人が後書きにも書いていますが、これは恐ろしき神が来訪し、帰還するという意味ではありませんでした。
神を招く者、として来訪したアスラ。そして、一人の人間として帰還するアスラ。
アスラという少女の心の来歴を示したタイトルでした。
殺める、ということ。
神という存在。
生きる、ということ。
人という存在。
ラストシーンは決して優しくないですが、だからこそ感じられる優しさというものが、確かに感じられました。
圧倒的な暴力は、快感です。
すべてを服従させ、従わせることはとてつもなく甘美な麻薬です。
幼いアスラがそうした力を手にしたとき、それに呑み込まれてしまうのは仕方のないことだとも言えます。
しかし、バルサは決してそれを許しません。
それは、暴力ではなにも解決しない、とか、人を殺してはいけない、とか、そういう通り一遍の善悪論ではなく(や、もちろんそれも多分に含まれてはいますが)、自らの経験と過去からそれを許さないのです。というより、許したくない、という方が正確。
短槍を人に向けるとということは、自らの心に向けているのと同じ。
人を傷つける、ましてや殺めるということは、軽々しく扱えるようなことではないのです。
それが、重い。
とても重い思い。
バルサはそれを言葉を尽くして語りかけるようなことはしません。
わずかな慈しみの言葉と、悲しげな瞳、自らの生きる姿を、アスラに見せるだけです。
しかし、そうして生きてきたバルサの姿は、なによりの言葉となり、アスラの心に染みこんでいきます。
「神の守り人」は『来訪編』と『帰還編』という風に命名されています。
作者本人が後書きにも書いていますが、これは恐ろしき神が来訪し、帰還するという意味ではありませんでした。
神を招く者、として来訪したアスラ。そして、一人の人間として帰還するアスラ。
アスラという少女の心の来歴を示したタイトルでした。
殺める、ということ。
神という存在。
生きる、ということ。
人という存在。
ラストシーンは決して優しくないですが、だからこそ感じられる優しさというものが、確かに感じられました。
この記事にコメントする
PR
カレンダー
最新記事
(12/16)
(01/25)
(11/03)
(10/31)
(10/11)
(10/11)
(10/11)
(08/28)
(07/25)
(07/12)
アーカイブ
